 男性芸能人
男性芸能人 木村昴は新小岩育ち!小学校から大学までの学歴と経歴紹介
木村昴さんの学歴と経歴を紹介。ドイツ生まれの彼は新小岩で育ち、声優として「ジャイアン」役を務める一方、音楽や舞台にも挑戦しています。
 男性芸能人
男性芸能人  女性芸能人
女性芸能人  スポーツ選手
スポーツ選手  スポーツ選手
スポーツ選手  女性芸能人
女性芸能人  女性芸能人
女性芸能人 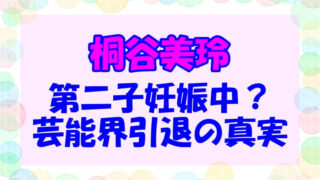 女性芸能人
女性芸能人 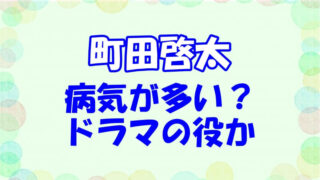 男性芸能人
男性芸能人  スポーツ選手
スポーツ選手  スポーツ選手
スポーツ選手